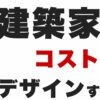佐屋香織さんのこと
私自身は神奈川県の鎌倉で生まれ育って、日本女子大学の大学、大学院を出た後、山本理顕設計工場に勤務し、ピークスタジオを設立しました。
同じく、チームの藤木俊大さんも同期で山本理顕設計工場に入所していまして、辞めた時期はそれぞれ違いますけれど、ピークスタジオを一緒にやろうということで、2014年に設立をしました。仕事がない中、アルバイトをしながら様々なコンペを出していく中で、南三陸町の町役場の仕事を取れたのをきっかけに2015年に法人化しました。今年の3月で丸十年になります。
普段私たちは建築の設計をしていますが、今まで関わってきた地域だったりとか、場所に対して建築を作って終わりではなくて、その後の使われ方に関わったり、イベント的に場所を作るだけもありますが、『場作り』ということを意識して設計活動をしています。

PROJECTのこと
・まちのはなれ
地域の事業者さんと並走しながら地域の価値を作り出したという集合住宅
・TACHIBANA HUT
自分達自身が事業者として場を作ることになった、地域と並走するParkPFI事業


まちのはなれ
川崎市は単独世帯が多く、中でも中原区は、それが全世帯の五割を超えていて、そういう地域というのは、家族世帯が多い地域と比べると地域自体の脆弱さというか、何か起きた時に単独世
帯の方々が孤立化したりだとか、困ったりするということが起こ
りやすい地域だなというのを感じています。
こういう考えに至ったのは、武蔵新城という街に私たちが事務所を構えていて、いわゆるワンルームマンションをたくさん所有されている地域のオーナーさんと知り合ったのがきっかけです。その方と、単独世帯の人々というのが、どうしても家に寝に帰るだけの場所になってしまうというのが、実際何か起きた時に不安だったして、少しでもつながりを持てるように地域に出てきてもらえるきっかけは、どうやったら作れるかみたいな話をしてきた
というのがあります。

2016年からカフェやワークスペース、イベントスペースなど、地域のオーナーさんが所有する隣接した物件の1階部分だけ整えてきた結果、面的な繋がりが出来てきました。『その街にある機能を使いながら暮らす』ということが、このまちのはなれのコンセプトです。街の中に銭湯やコインランドリーがあったりだとか、食事するところがあったり、仕事する場所があったりしたら、街を使いながらコンパクトに建物の中で暮らすことができるんじゃないかと。また、街の中で住んでいる人がもう一部屋借り足すとか、仕事部屋として借りるみたいな、そういった可能性もあるんじゃないかということで、相互に機能を補完し合いながら、建物自体単体で完結しないということを目指しました。


TACHIBANA HUT PARK PFI
自分達自信が事業者になったのが、川崎市の橘公園のPARK PFI事業です。
橘公園は17,000平米ほどある近隣公園で、その中にある公園事務所を利用した事業になります。
川崎市の道路や公園を管理する公園事務所が10年以上前に移転し建物自体が使われなくなって、しばらくそのままでした。使われていなかったってこともあったので、公園に来る人たちはここが元々どういう場所だったかっていうことをほとんど知らない状況でした。そして、橘公園は2019年に川崎市のサウンディング調査の対象となり、その2年後に橘公園の魅力向上のための社会実験が実施され、私たちは1ヶ月間参加をしました。
私たちは、この場所を更地にして新築するのではなく、今建ってるものを良くするということの方がこの公園にとっ
てよいんじゃないかということで、改修するということを選択しました。また、管理事務所として入ることになるので、建物全体にテナントを入れて専用させてしまうのではなく、場所貸しや時間貸しという形で、いろんな人に使ってもらうような事業にしました。


1階部分は、レンタルスペースで、イベントをしたり、大人数で食事をしたりできる大きい部屋を用意しました。
また、シェアキッチンは菓子製造業許可を取ってあるので、ここで作ったお菓子を別の場所で販売できるようにし
ました。併設するショップでは、別の場所で作ったものを持ってきて、販売できるようにしています。どちらも時間
貸しや売上の何%かを利用料としています。
2階はピークスタジオの事務所とコワーキングスペースを作り、管理運営を自分達で行っています。元々の建物とは別にカフェスタンドを木造で建てました。武蔵新城に元々あったカフェに声をかけてプロポーザルの時から入ってもらって一緒に提案をしました。
コミュニティファームの運営・管理はNPO団体さんにお願いしています。野菜販売やコンポスト講座などのワーショップもあわせて開催してもらっています。


CROSS TALK
Q
いわゆるクライアントから設計依頼を受けて建築を作っていくのとは違って、街づくりや街おこしに近い活動ですが、共同住宅の案件では一つの建物で完結せずにまちに開くことを意識されるきっかけみたいなものは?
A
私たちの師匠である山本理顕さんが、『人と関わらずに生きるってことは難しい』という話をよくされていてました。私たちは一年目に東京の中央区にオフィスを借りて活動してたんですが、ただ仕事を待っていても来るわけでもありませんでした。地域との関わりがないまま活動していると、暮らしの実態がないような感覚になったというのもあって、人との繋がりを求めて武蔵新城の事務所に移転したんだと思います。
南三陸町の役場のコンペの時にも提案させてもらったんですけど、ただただ機能を詰め込んだ役場ではなくて、ふらっと人が立ち寄れるような屋内広場を設けました。いかに人が交わるというか、何かこう偶然にでもきっかけが生まれるような場所みたいなものは、意識しているんじゃないかなと思います。
Q
集合住宅の案件では、カフェなど何件か展開されてましたけど、全て同じ地主さんですか?
理解のある地主さんとどうやって知り合えたのか?
あの熱意だけではなく収支とかそういうことも含めて、どこまで提案をされてるのか?
A
地主さんとの出会いっていうのは、偶然なんですが、同僚の藤木が、最初に建築の設計ではなくてその
会社のロゴづくりのための街歩きマップを作るお仕事から始まっていて、一緒に過ごす時間を経て、ピークスタジオにカフェの設計を頼んでくださったんです。提案を気に入っていただいて、このエリアを良くしていくのに力を貸してほしいということで、誘ってもらったのがきっかけで武蔵新城に移りました。この地域で何棟も持ってらっしゃる方です。
賃貸の集合住宅は綺麗に内装を整えたら最初のうちは人は入るけど、次第に綺麗な新しい物件に負けていってしまうっていうところに対して、建物単体ではなくて、『街の価値を高めて』住んでみたい街だと思ってもらうようにするっていうことが、自分たちがこの集合住宅を持っているオーナーとして必要なんじゃないかと。街が良くなれば部屋の内装だけに左右されず、多少古くても住みたいと思ってもらえるだろうし、自分たちのところだけが単独で勝つとかではなくて、地域全体が潤っていくっていうような視点をもうすでに持ってらっしゃっていて、そういったところを聞きながら、一緒にいろいろやれると面白いんじゃないかということもあって武蔵新城に移転をしたというのがあります。
私たちの事務所が入ったダイロクパークという建物があります。ここの1階の左から2件目に移転してきたんですけども、最初は本当にただの共同住宅だったんです。この道路際にブロック塀が建っていて、門扉もありすごく閉じたような感じでした。当時は16部屋あったうちの4つぐらいしか人が住んでなかったと思います。
私たちがここに入るときに壁を撤去して、道路側から直接階段でアクセスできるようにしたいという提案をしたところ、いいよって言って快諾してくれました。
道路側をオープンにしてアクセスできるようにしたところ、一階部分に店舗で使いたいっていう人たちがどんどん出てきて、一番右端がお菓子屋さんでその一軒隣がイタリアのデリが入っていて。私たちの左隣っていうのがレンタルスペースみたいな形で入っています。二階とか三階にもちょっとした個人的なサロンをやってる人が入ったりだとか。あと、訪問看護のステーションが入ったりだとかってしながら、いろんな使われ方をしだしたっていうのがありました。それをきっかけにいろんな人とつながりができてきたなと思ってます。なので、やっぱり私たちの力だけではなくて、この場が持つ力っていうものが人をどんどん引き込んできたっていう経験をしました。
Q
私も大阪でパークPFIの話があったんですけど、踏み込めなかったんです。それは金銭的なことと時間的なことで、こんなんしてたら設計の仕事どうなるんやといろんな不安で踏み込めなかったのです。建物を改修するっていうのも当然お金もいるし、テナントの調整や誘致とか、そういうことにも時間かかると思いますが、それをどのようにクリアされたのか教えてください。
A
まず時間は、純粋な設計事務所に比べると取られるところはあります。
レンタルスペースを週末借りたいっていう人がいると、その時間ちゃんと利用できるように張り紙をしたり。普段カフェスタンドの客席にも使えるようにしてあるので、席数の調整とか連絡したりとかってどうしても時間を取られるなとは思ってます。そこは設計スタッフも頑張ってその部分を担ってくれたりだとか。イベントで知り合った方々に作業を手伝ってもらいながらやったりとかしています。
事業に関しては、川崎市の事業ということで、地元の信金さんが比較的協力的でした。
また、補助金が取れたので、なんとかなるかなという感じです。
この公園は建物だけの事業を見ると、人に貸す時間が取られて大した収入にならないんですけど、公園の中に駐車場がついてまして、元々その駐車場の収入が比較的大きいのと、あとはカフェスタンドからのテナント料ですね。図面には載ってなかったんですけど、建物の裏に元々倉庫があって、そこにイベント会社さんに一部その場所を使ってもらってします。そのイベント会社さんが持ってるテントとか椅子とかテーブルとかっていうのはそこに入れてまして、うちがイベントをする時には安く貸してもらえたりだとか。逆にその方々は場所として使える使いやすいところなので、協力的に運営してもらったりだとかしてるっていう感じです。植栽屋さんも倉庫を借りてくれてるんですけど、この建物の植栽も管理してくださっていて、なんかそういうその連携を取れる方に借りてもらってるっていう感じです。まだ一年経ってないのでどこまでうまくいってるかっていうのが自分たちもあんまり把握できてないんですけど、今のところそんな感じでやっぱりやってきた。社会実験を一ヶ月やった時に知り合った方とかもいて、つながりも使いつつ始めています。
Q
PARK PFI事業を説明していただけますか。
A
民間の活力を使って、公共の場所を整備運営していく仕組みの一つです。行政が整備して運営だけ民間というパターンもありますが、今回の場合は民間が整備して民間が運営しています。このPARK PFIで求められてた条件とし、この場所を活用して事業を行って公園の価値を高め還元することです。公園の中にある公衆トイレが和式で、ちょっと汚かったりとか暗かったりとかしたんですが洋式に変えて明るくするということで一つ還元しています。公園全体で17,000㎡もあるので、公園全体の管理を全部やっているっていうわけではなく、元々公園自体を管理している道路公園センターがグラウンド等の貸し借りや植物とかの剪定もそのままやってもらっています。私たちは日常的にゴミを拾ったりとか、不法投棄されてたりするものをチェックしたりだとか、そういう見回りみたいなものは日課で一日一回するっていうルールになっています。
公園にスターバックスが入ればいいっていうようなプロポーザルじゃなかったですよね。定期的に地域のイベントを開催して、近隣の利用者さんの満足度を高めるっていうようなことをするっていうものを求められていました。なので、事業としては何やっても本来はいいんですが、公園の施設なので、誰かが専有するのではなくて、みんなが使えるような施設にするっていうことが条件でありました。イベントの告知とかチラシ作りとかは外部に出したりとかしますけど、当日のテント立てたりとかイベントに来た人を調整したりとかイベント全体の運営は自分達で行なっています。
Q
川崎で活動されていることでどんなこと気をつけていますか?
A
やっぱり最初は、川崎市って比較的怖いイメージが強かったんですけど、中原区って川崎市の真ん中辺
で、それもそれなりに発展して、比較的ローカルな感じがします。川崎の南の方に比べると穏やかなんで
すけど、でも武蔵新城はちょっとまだ好き嫌いが分かれるかもしれないですが、居酒屋もたくさんあって、活気があるんですよね。商店街には個人店がいっぱい入っていて、商店街があるから楽しいって住んで
る人と、うるさいから嫌だっていう人がいるだろうと思います。一方で、ラーメン屋さんとかカレー屋さんとか、男性が好きそうなお店ばっかり。なので、カフェを作ると今までいなかった層のお客さんが出てくるみたいな印象がありました。子育てのお母さんとか若い主婦の方とか、高齢のおばあちゃんやおじいちゃんが来てくれるよう
な場所になったんです。ラーメン屋さんとかにはいかないような人たちが街に出てきて、そこで一緒の空間で過ごすことで顔見知りになって繋がっていくみたいなことが起きていくっていうのを見た時に、その場所なのか、そういう空気感なのかわからないですけど。どこかにいるだろうっていう属性の方がいやすい場所ができるっていうのが一つ大きいのかなという感じはしました。この辺に無いものを作ってみるっていうことは一つあるのかなって。

Q
山本理顕設計工場時代のエピソードを教えてください。
A
私はとにかく怒られる役だったので、怒られてた記憶しかないんですけど。。。
よく『本気でやれよ』って言われてました。スタッフとしては本気でやってるつもりなんですけど。
でも今自分のスタッフに本気でやれよって思ってるから、やっぱ同じことを感じるんだなって思いますね。
Q
収支をプラスに転じた要因を教えてください。
A
この活動自体が宣伝というか、広告になっていて、PARK PFIの設計相談みたいなものはちらほら来ていて、PFI事業に関わらず、仕事の幅が広がることで、設計の仕事につながるかなというのはちょっと思っていま
す。
収益性は、それぞれの場所の条件によるのかなという気がします。単純に大手が入ってスターバックスができた方がいいなっていう思いももちろんありますし、その付加価値というか、その建物以外の部分での収益がありそうな物件だと可能性はあるのかなと思います。
Q
PARK PFIの運営について教えてください
A
イベント自体は企画から告知、イベント出店する人への連絡、当日の設営や撤収の補助とか全部やります。写真や記録を撮ったりもしてます。出店料は当日精算して回収する感じです。
イベントの頻度は、今のところ年に三回とかで、連日あるわけではないので、無理のない感じで対応しています。
イベント自体はただのイベントで終わらないようにしたいなというのは思ってまして、せっかく公園があるので、公園に来た子供がただ遊んで帰るだけじゃなくて、学びを得るとか、自然のことを知れるとか。物を買って終わりではないような体験ができるとかっていうことが、今後定着していくといいなって思っています。
カフェスタンドのテナントの賃貸借契約とかは、地元の不動産屋さんに入ってもらってやっています。レンタルキッチンやコワーキングスペースの場所を借りる方々のために利用規約は自分たちで作ってま
す。
キッチンを借りる人は食品衛生責任者の資格を提示してもらって契約してもらいます。事業に関わるところは、基本的に自分たちで対応してまして、市との協議内容に即して、色々なことを展開しています。
Q
近隣との関係はどうですか?
A
入居してから音の問題を指摘されたことはあります。どうしても夜中に作業する必要があって、作業していたら近隣の方から連絡をもらったりしたので、そういうものは挨拶に行って謝ったりとかして、その都度対応してるっていう感じです。

去年の夏にやった映画上映会は、いい音響を使ったので比較的大きな音が出ていました。公園の外の住宅地まで音が聞こえてたんですけど、特にクレームもなく、逆に、なんかいいイベントやってくれてありがとうみたいな感じで言ってくださる方が多くて、やる内容にもよると思いますが。ただ音が大きいだけでクレームが来るっていうような感じではなくて、やってることに対する理解だったり関係性が大切なのかなと思います。イベントで出店された方がお酒を売ったりしてたことがあったんですけど、別に法的な問題があるわけではないので、子供だけではなく大人が楽しめる公園として、その辺はちょっと今後様子を見ながらかなという気はしてます。